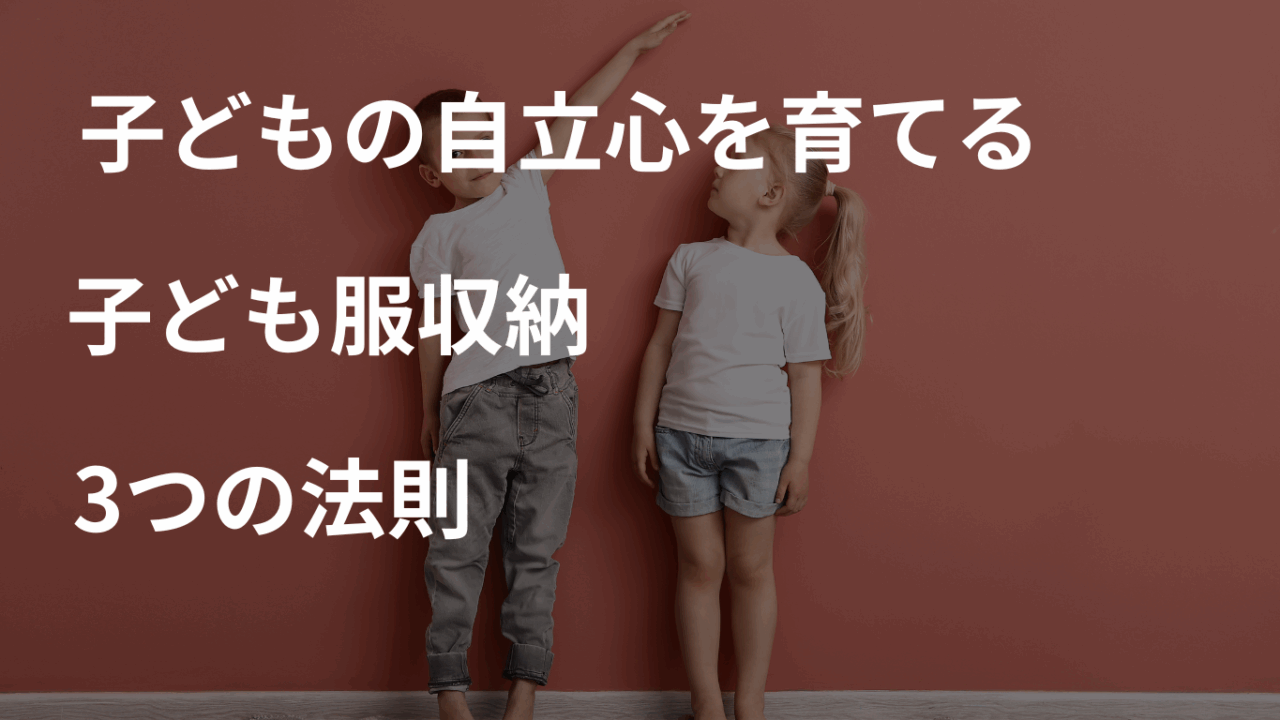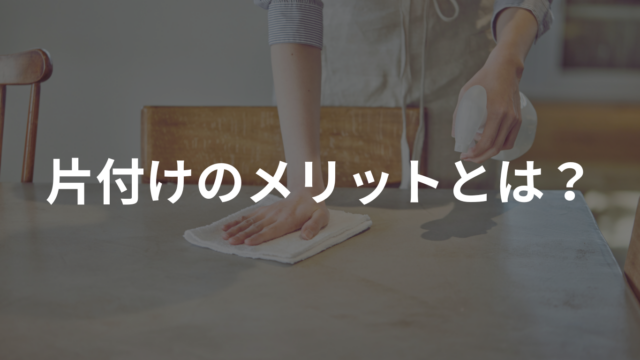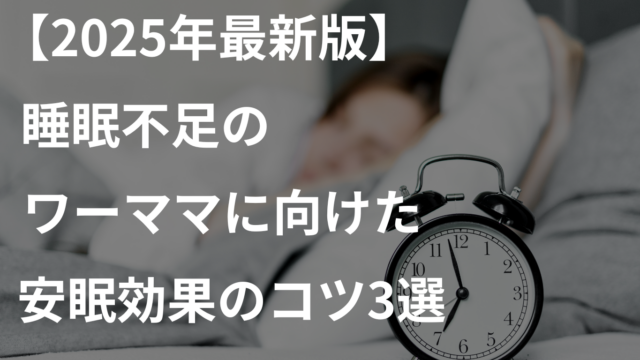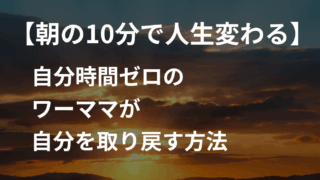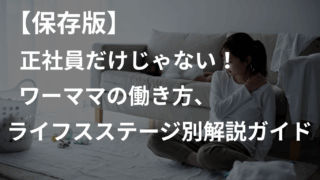こんにちは! 3児のフルタイムワーママのかえです。
仕事・家事・育児で忙しいワーママに向けて片付けや時短家事によって
今よりもっとラクに生活できるコツを発信しています。
・着替えの度に「ママー!」と呼ばれるのがストレス
・子どもの服は毎日枚数が多くて干すのも畳むのも大変
・そろそろ子どもが自分で身支度ができるようになってほしい
子ども服の管理を今よりもっとラクしたいと思う方は
ぜひ最後までお読みください!
ワーママ流・子ども服収納|3つの法則

毎朝の「この服どこ?」攻撃から解放されたい一心で、色々な収納法を試してきました。
ポイントは「子どもが自分で考えて選び、片付けられる」仕組みづくり。
私が辿り着いた「ワーママ流・子ども服収納メソッド」は、次の3つを意識しています。
1. 引き出しは「軽い」「低い」「奥行きが浅い」を重視
2. 子ども服の収納場所は、家族みんなの生活動線上に作る
3. 「完璧な収納」より「維持できる仕組み」
この記事では、我が家で実際に効果があった方法と、
いかにラクに収納できるかをお伝えしていきます。
では具体的にどんな収納方法にすればいいのか?を次の章で紹介していきますね。
1.引き出しは「軽い」「低い」「奥行きが浅い」を重視
子どもが自分で出し入れできるようになるにはまず
「分類」より「出しやすさ」を意識ことが大切です!
それを叶えるには、
「軽い」・「低い」・「奥行きが浅い」
の3つが必要となるのです。
具体的にはこのような商品です。
ぜひ、子ども目線になって収納ケースを選んでみましょう。
2.子ども服の収納場所は、家族みんなの生活動線上に作る

2つ目のコツは、収納場所を家族みんなの生活動線上に作ることです。
なぜならば、生活動線上にある=子どもが普段動くエリアに収納があるため、
この一連の動作が自然にできるようになり「習慣化」しやすいためです。
3.イラストや文字でラベリングする

子どもが自分でできるようするには一目で分類がわかることが大切です。
文字が読めない年齢のお子さんの場合はイラストで表すと良いですね。
どうする?まだ着られる服の上手な手放し方
まだ着られるけど着そうにない、、、。でも、保管場所はもうパンパン。
捨てるのは罪悪感があるしもったいない。そんな時の手放し方をご紹介します。
1.譲る
状態が良く、まだまだ着れるものは誰かに譲る方法もあります。
近所の子や、保育園に寄付する方法もあります。
相手の負担にならないよう、相手の反応も見ながら進めていきましょう。
2.売る
売ってお小遣いを稼ぎたい方は
メルカリやフリマサイトで売ることがおススメです。
フリマサイトで売る手間が面倒と感じる方は
リサイクルショップで売ることがおススメです。
買い取り金額は期待できませんが、一気に減らすことができます。
3.捨てる
譲る・売るに当てはまらないものは潔く処分する!と決めておくのもひとつの手です。
切って雑巾代わりにするなど、最後まで活用することができます。
お下がり服はもらわない選択もアリ!上手な断り方3つのコツ
お下がり服について、こんな事を感じたことはないですか?
・気持ちは嬉しいけど好みが違う、、、
・服は足りているけど、断り切れない、、
・いつ着せよう、、
相手との関係性にもよりますが、よかれと思って譲ってくれる人に対して断るのは
罪悪感を感じますよね。
そこで角を立てずに上手に断る方法をご紹介します。
1.「収納スペースが足りなくて、、、」と環境のせいにする
自分や相手のせいではなく、物理的に無理なんだとやんわり伝えられます。
2.「もう充分な量はそろっていて!」+感謝+完結で伝える
「気にかけてくれてありがとう!でも今ある分で充分足りているかた大丈夫だよ。」
と伝えましょう。
3.「使いこなせるか自信がなくて、、、」と自分側の事情にする
「せっかくもらってもサイズ管理できる自信がなくて、、、」
と相手を立てながら断れるので、親戚や目上の方にも使いやすいワードです。
まとめ|子どもの自立心も育てて家事ラクも叶う

子どもが自分でできる服の収納を整えることで
・子どもにとっても「自分でできる」自立心を育てる
・「子どもができる」=「親の手があく」=「家事の時短になる」
が叶います!
「忙しいからこそ、シンプルに」。
子どもが自立して、ママの家事負担も減る。
そんな一石二鳥の収納法を一緒に見ていきましょう!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。