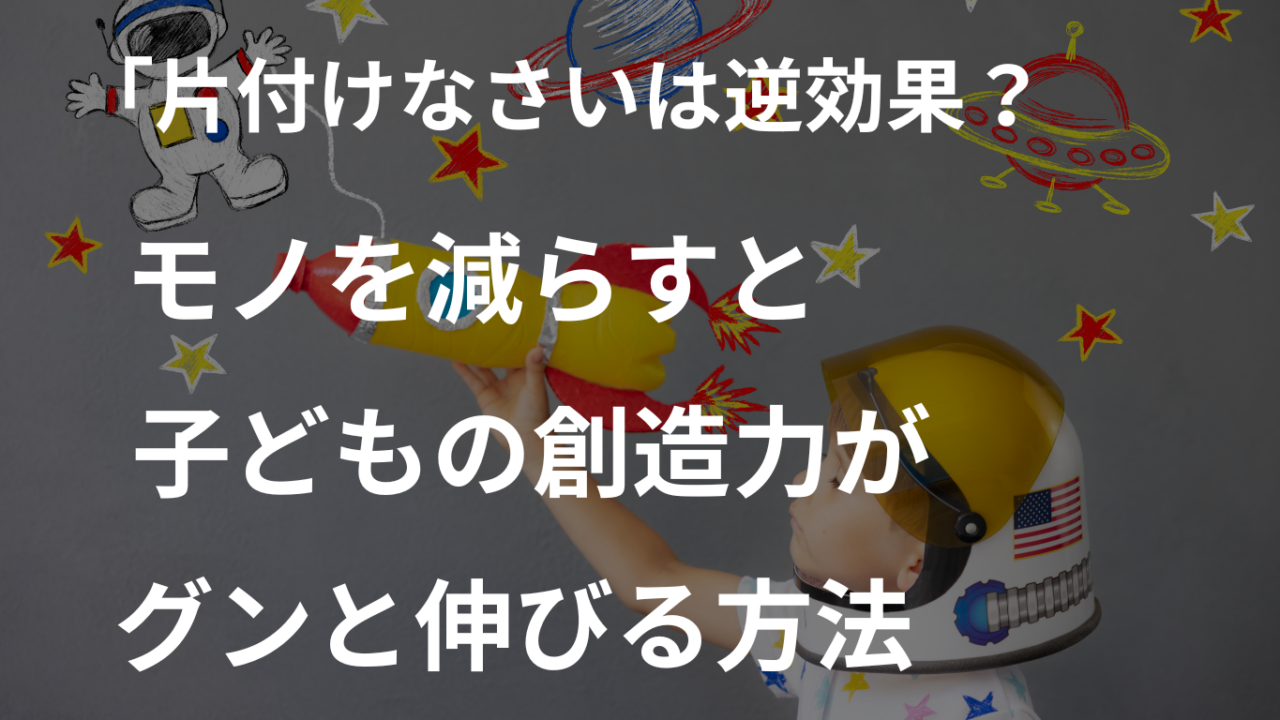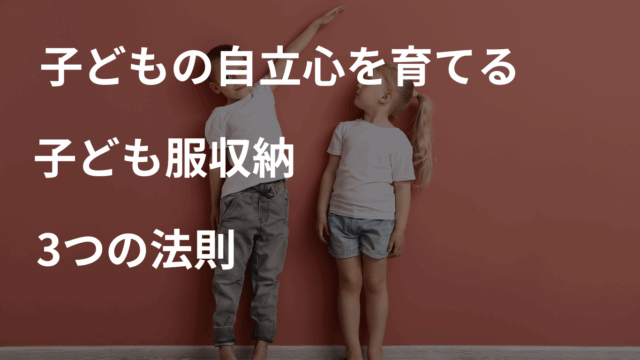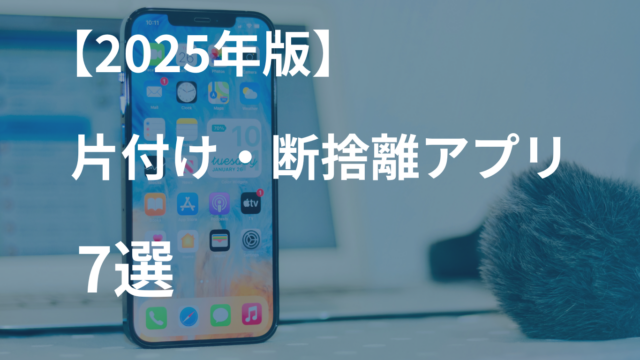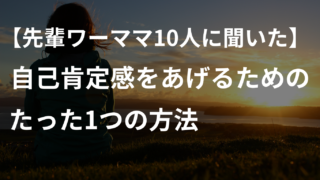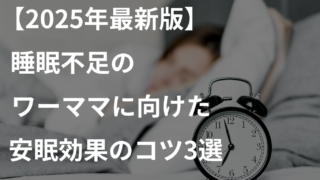こんにちは!
3人の子どもを育てながらフルタイムで働くワーママ、かえです。
「片付けって、ただでさえ忙しい毎日に本当に必要?」と思っていた私ですが、
少しの工夫で、ぐっとラクで快適な暮らしができるようになりました。
このブログでは片付けや時短家事によって疲弊しているワーママが少しでも快適に過ごせる方法をお届けしています。
・仕事、家事、育児にいつも時間が足りない
・部屋の片づけがとにかく面倒で後回し
・子どものおもちゃが多くて片付けの度にうんざりしてしまう
朝から晩まで、ワーママはとにかく時間との戦い。
特に、子どものおもちゃが散らかった部屋を見たとき「あぁ、またか、、、」とうんざりしてしまうのではないでしょうか。
・子どもが楽しく遊んでくれるのは嬉しいけれど、遊んだあとの片付けの事を考えるとあまりおもちゃを出してほしくない
・親が片付けさせなきゃと思うほど、子どもは反発しやすい
「片付けなさい」と言っても子どもがすんなり動くことってなかなかないですよね。
今回は、そんなモヤモヤしているあなたに
「片付けなさい」はなぜ逆効果なのか?
についてお届けしたいと思います。
1. 「片付けなさい」はなぜ逆効果なのか?
「片付けなさい」はなぜ逆効果なのか?
子ども自身「もっと遊びたいから片付けたくない」という理由ももちろんあります。
しかし最大の理由は、「片付け」=「やらされている」と感じるためです。
「片付けなさい」と言われることは、子どもにとっては指示されているように感じ、
「片付け」は楽しいものではなく「嫌なこと」となってしまうのです。
では、なぜ片付けは「嫌なこと」となってしまうのでしょうか。
それは、実は子どもは「片付け」の言葉の意味を理解していないためです。
そして、さらに子どもの脳の仕組みにヒントが隠されている事がわかっています。
脳の仕組みと聞くとなんだか複雑そうと思うかもしれませんが、
この仕組みを知ることによって、子どもが自分がとる行動がわかりやすくなり、
結果、自分で片付けられるようになるのです。
子どもの片付け嫌いには脳の仕組みにヒントがある
では、子どもの片付け嫌いには脳の仕組みとは何なのか?
それは結論、実は脳の空間認知力が未発達なためです。
空間認知能力とは?
「物の位置(いち)や形(かたち)、向き(むき)などを
頭の中でイメージして考える力」
少し難しく感じるかもしれませんが、これは「大人と子どもの脳の違い」を表しているんです。それはどういうことか話していきますね。
「片付け」と一言で言っても、
①物を「分類」する
②「どこに戻すか」を判断する
③「手を動かす」
という複数のタスクが必要ですよね。
これは大人にとっては当たり前でも、実は子どもの脳にはとても高度な作業になるのです。
複数の工程をふむことは大人でも「面倒だな」と思いがちです。
それが子どもであれば途中で面倒になって「やーめた」となってしまうのも無理はありません。
特に幼児〜小学校低学年のうちは「空間認識力」や「ワーキングメモリ(作業記憶)」がまだ未発達。
小さい子は「片付けの意味」自体をまだ理解していないのです。
じゃあ、どうすればいいの?
では、そんな「片付け」自体の意味をあまり理解していない頃の子どもにはどう伝えていけばいいのでしょう。
それは、ずばり
わかりやすく、具体的な指示をだすことです。
具体的にいうと
・「ブロックをかごの中に入れてね」
・「ぬいぐるみをベッドの上に戻そうね」
・「絵本を本棚に立ててしまってね」
という伝え方です。
具体的にとってほしい行動を伝えることで、すること・やることが明確になり、
結果、片付けている状態になるのです。
大人が思う「片付いた空間」と、子どもにとっての「居心地のよさ」は違う
大人は片付いた空間の方がスッキリしていて良い、心地良いと感じる人が多いと思いますが、
子どもにとっても片付いた空間の方が良いかと言えば、実は違うのです。
では、子どもにとって「居心地の良い空間」とは何なのでしょう?
それは、
・信頼できる大人がいる 「心の安全」
・ありのままの自分を受け止めてくれる「”ここが自分の場所”と感じられる空間」
なのです。 子どもにとっては「部屋が片付いてスッキリしていている」=「居心地が良い」ではないのです。
むしろ、自分の好きなものが常に手に届く場所にある方が子どもにとっては
「居心地が良い」環境になるのです。
おもちゃが多すぎると、創造力はかえって育たない?
おもちゃがたくさんあると目移りして遊びが浅くなりがち。
モノに遊びが決められていて、創造力の余白が少なくなりがちです。
逆におもちゃが少ないと得られる効果としては
・ひとつのモノで長く、深く遊ぶ
・想像力で子どもが自分で考えて遊びを作ることが増える
・「ないなら工夫しよう」と試行錯誤する力が育ちやすい
などのメリットがあげられます。
与えられたモノでの遊びは「自分で考える・創造する」というチャンスを減らす可能性があるのです。
実は「選択肢が多い=自由」ではない
子どもは目新しいおもちゃを見ると「欲しい」と飛びつきます。
しかし、買ってあげてもすぐに飽きる、、、。
そんな風に感じたことはありませんか?
そして、選ぶほどおもちゃはあるのに子どもは満足しません。
実は、選択肢が多いと迷って決められないのです。
それは子どもが大人よりも判断力が未熟で、選ぶだけで疲れてしまい、
どれもしっくりこない=「どれも楽しくない」状態になってしまうからです。
選ばせること=自由ではなく、選びやすいように整えることこそが本当のサポート。
選びやすいようにするとは、つまり選ぶ数を絞る・少なくするのが効果的と言えます。
ちなみに心理学では、
「人が無理なく選べる選択肢の数は 3〜5個程度」
と言われているようです。
おススメの方法
おもちゃ箱を2〜3グループに分けて、1週間ごとに入れ替える。
→ 「久しぶりに出てきた!」と新鮮な気持ちで遊べて、選びやすさもアップ!
引き出しにいれても子ども自身で出せる場合は一旦見えない場所に保管する方法も効果的です。
ぜひ一度実践し、お子さんの変化を感じてみてください。
何もないところで「工夫して遊ぶ」ことが創造力を伸ばす土台に
極端な話、子どもは安心できる場所であればおもちゃがなくても遊ぶ「天才」です。
ルールや使い方が決まっていない環境だからこそ、「どうやって遊ぼう?」と考えること自体が創造的。しかも子どもはそれを「苦」とは感じず楽しんでできるところが子どものすごいところ。
何かを見立てたり発明したりすることが、子どもにとっては集中できる楽しい時間なのです。
例えば、
・段ボールで電車ごっこ
・積み木を建物にみたてたり、積み木1個を人に見立てる
・ペットボトルのキャップを転がして遊ぶ
など、おもちゃがなくても身の回りのモノも遊びに変えてしまうのです。
まとめ
子どもの脳の仕組みを知ることにより「片付けなさい」という言葉より、
他の言葉で伝えていく必要性を知っていただけたのではないでしょうか。
家事をしながら子どもの面倒をみているワーママさんは多いと思います。
家事に集中したいから子どもはオモチャで遊んでいてほしい、
そのため、子どもが満足するためにとオモチャをつい与えてしまうかもしれませんが、
モノの多さが返って子どもを飽きさせる要因になることも知っていただけたと思います。
子どもにとって大事なのはオモチャの多さではなく、
信頼できる大人と自分の安心できる場所で遊べること。
このことがわかれば、たくさんのオモチャは必要ないことがわかります。
また、子どもに片付けてほしいと思ったら具体的に、わかりやすく伝えましょう。
これを実践し、子どもにとってもママにとってもストレスの少ない日々を目指しましょう!
本日は最後までご覧いただきありがとうございました!